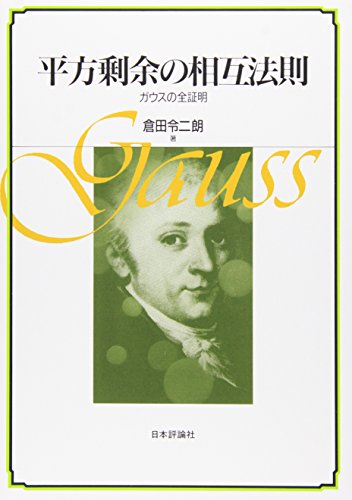markovproperty.hatenadiary.com
なかなか進まない。
”the least”の意味論が「絶対最大級」で、限定(永続的な属性)にせよ叙述(永続的/一時的;属性に関して中立)にせよ、比較としての相対的な修飾ではなく、「比較」の表現を伴った実際は比較でない二次的な修飾だ。
それは、比較(最大)が可能なとき表現として「比較」(「最大」)が可能であり、意味が可能なとき、意味を括弧に入れた操作が可能であることと平仄が合う。
すなわち、数は意味か操作かを考えたとき、「数が操作である」を特徴づけるのは、語彙が持つ【包含性】(静態的,分析的性格)と【推移性】(動態的,統合的性格)であると思う。
- 数が操作である
- 【包含性】
「意味を対象とする」ときに、対象を意味化することができる
Pを意味とするとき、{P}ならば、{}を、P’として、Pから中立に考えられる。
- 意味と「意味」をクラス分けできる
- クラス内で意味を分割できる
- 【推移性】
順序を構成できる
操作が順序を持つことから、数も順序を持つ
- 【包含性】
このように「1」と「数(多)」の関係を、「操作」化すなわち操作の意味化から、「意味」と「操作」の関係に整理したときに、「1と数は対立する」ことの意味が見えてくるような気がする。要は、スティブンは、「1」から「多」を構成できるとき、1でなくてもよいのは「「」が「ある」からだ」と数の偶有性を喝破したのだ。そのとき、括弧しか「ない」のであるから、基数はゼロでよい。not only number but "n""u""m""b""e""r"である※。
※「白馬は馬に非ず」を、White horse ”is not only” horse ,”but” white. と言うのは、A white horse ”is not” a horse との比較において、”a”であるかどうかである。そうでないと、馬の存在性から、馬でないことはない、だろうと思うこととなる。馬に着目して猶、「白」の偶有性(クラスの違い)を強調しているのであると思う。すなわち、偶有とは表示である。すなわち、「表示」とは、分岐(条件)に関して、マーカブルと言っている。
「数」と書けずして、数ではない。操作なくして数ではないのことの含意であり、「操作できる」とは「意味化できる」という意味である。
意味化できるとき、意味化に一般性を見出すのであるから、そのときに限り、対象となった意味は「」(「(ない)」)のであった。
一般向け解説では、2がほとんど説明されず、直観的である。数もテキストに過ぎないことが直観主義から忌避ないし警戒されているのかもしれない。
古代から中世にかけては「操作」と言わずに「運動」と言った。これが近代にかけて、例えば惑星の運動のように、物理学の「運動」と混同されたかもしれない。むしろ、近代より前には、哲学であった。
「対立する」の叙述性であり、「対立」の語意だ。それが「一般的」であるならば、「1から」という統合的な理解ではなく、分析的な理解に立ち、「どのような構成を取ろうとも、共通して1を見出すことが可能である」という包含性の叙述である。
別の言い方をすれば、数は比である、ということである。1は比に係らず自明である。
このとき、比とは分割操作の結果であり、1は分割の元であって、分割されて在る対象の例外である。本当のところは、永遠に分割されても残る、最後の「1(つ)」であるが、この「1」に関して言えば、「分割されていない」と形容される。これが「本質的」の意味論である。
したがって、「対立」は「対比」であることの帰結である。
また、だから、モナドと、言及的な意味で、基本構造は同じである。
要は、数とは属性であり偶有に過ぎないから、一般的性質を持つが、係る本質自身から区別されるということである。数にとって、1が本質であり、数自身は「多」と謂う本性たる偶有である。それが「偶有」(偶々)であるのは、操作の具体性に依存するからである。反対から言うと、本質たる「1」に、具体的な操作「以前」を、「どのような操作を取ろうとも」と仮想でき、これが「一般性」の定義となっている。したがって、「1」は「一般的」であるがゆえに「本質(的)」である。
これが「プラトン」(アリストテレス)の主張のはずであり、ガザーリーはこれを批判したはずである。
そしてそのまま、その「批判」が、ライプニッツの「モナド」すなわち「実無限小」と平仄が合うようだ。
デモクリトス(引用者註:ライプニッツ)の考えを実現するには,実数の全体に新しく無限小あるいは無限大と呼ばれる数をつけ加えねばならない.
P.19,極限概念,『数学100の発見』
1961年アブラハムロビンソン(1918-)は実数の全体から,これらの無限小や無限大をつくりだすことに成功した.極限概念を含む初等解析学はルクセンブルクによって新しく構成された.
同前
「各実数にはそこに無限小がたくさんくっついており」、例えばπについて言えば、「πにくっついた無限小は
π=3.1415・・・;0a1a2a3・・・a・・・
なる形をしている.ここでai は0,1,2・・・,9 のいずれかである」(P.19)
(実際に現代の数学から比較した人のサイトを以前リンクしたはずだが、失念してしまった。また探す)
このとき、ε-δ論法は姿を消す。反対から言うと、「姿を消す」ことにε-δ論法の意義がある。
これをスティブンの小数表記と比較すると興味深い。
イスラム数学の表解(商業数学)から発展したと思しき小数は、(そもそも計算表を基にした)「諸元」に拠る操作概念だったようである。⓪①②と付番してゆく操作が特徴である。要は、スティブンは以下の2つに気が付いたようだ。
- 数は表から成る
- 表は表であって数自身ではない
係る古典的なイスラム数学は、このような数を「見える化」したものと考えることができる。
こうして、ガザ―リーの〔第十八〕問題とライプニッツの叙述を比べると、おどろくほど問題の対象が近い。
「第10証明」と「第7証明」の構成方法の違いなどはどうであったか。
ゆえに1/2(φ+1)は偶数.ゆえに
(q/PP’)=1
P.51,第1章相互法則の第Ⅰ証明,『平方剰余の相互法則 ガウスの全証明』
すなわち、ガウスは、どれだけのかずのクラスを持てば十分かを言っており、そのとき、添え字は「マーカブル」(偶有の「しるし」)だと言っていると思って、差し支えないだろうか?知らない。
したがって、最上級が単数を指示するとき、「もっとも」と名詞を修飾する形容詞の意味論に従っており、複数を指示しうるとき、「修飾する」ときの偶有性に根ざしていると思って差し支えないだろうか。
これが、”the least”が”merit”(複数形)を伴うときの、いまのところの、説明である。
意味論的には「絶対的最上級」で実際は比較と関係がなく、構成的には偶有性であることから動詞が複数形となる。これが形容詞が叙述の位置にあるとき、永続的/一般的属性から中立であるために、混乱する。